人手不足が叫ばれる日本社会。しかし、その一方で長年にわたって就職や労働環境で不遇を受けてきた「就職氷河期世代」は、いまだに報われない状況にあります。なぜ企業はこの働き盛りの世代を活かしきれないのでしょうか?本記事では、氷河期世代が置かれてきた立場・パワハラ問題・そして人手不足社会との矛盾を、多角的に解説します。
就職氷河期とは?氷河期世代の定義と背景
バブル崩壊と採用縮小の時代
就職氷河期とは、1990年代半ばから2000年代前半にかけて、新卒採用が極端に縮小された時期を指します。この時期に学校を卒業した人々、現在の40代半ば〜50代前半を「氷河期世代」と呼びます。
彼らは「新卒で正社員になれない=キャリアがスタートできない」社会構造の中に置かれ、非正規雇用やアルバイトで生活を支えるしかありませんでした。
個人の努力ではなく“構造の犠牲”
「努力不足」「甘え」などのレッテルを貼られることもありますが、それは的外れです。当時はそもそも求人がなく、チャンスがなかったことが大きな問題であり、個人の責任に帰するものではありませんでした。
日本特有の「新卒一括採用」「終身雇用」文化により、キャリアの“乗り直し”が困難だったことも、彼らを長期的に苦しめる要因となりました。
企業が人手不足でも氷河期世代を活かせない理由
年齢で選ばれる就職市場
今、企業は「若くて長く働ける人材」を優先して採用する傾向があります。即戦力かつ柔軟な人材を求めるなかで、40代・50代の未経験者は門前払いされがちです。
その結果、「人手不足なのに採用されない」という矛盾が、氷河期世代にとって現実のものになっています。
スキルより“年齢と雰囲気”が見られる面接
氷河期世代の中には、長年の非正規雇用でスキルを蓄積しづらかった人もいます。しかし、それ以上に問題なのが、年齢や雰囲気による主観的な判断で面接を落とされることです。
「扱いにくそう」「年上の部下は嫌だ」という偏見が、今なお現場に根強く残っています。
氷河期世代が受けてきたパワハラの現実
バブル世代からの“無理解な圧力”
バブル世代が管理職・役職者となった2000年代以降、氷河期世代はその下で働く立場になりました。このとき、**「根性論」「指導という名の威圧」**が職場で横行し、多くの氷河期世代がパワハラに苦しんできました。
-
「昔はもっと厳しかった」
-
「根性が足りない」
-
「それくらいやれないと社会人じゃない」
こうした価値観の押しつけは、単なる世代間の意見の違いではなく、職場での支配・抑圧につながる構造的パワハラです。
未だに残る“沈黙の上下関係”
さらに現在でも、バブル世代が企業の上層部に残っているケースが多く、氷河期世代は「上にも逆らえず、下からは理解されにくい」という難しい立場に立たされています。
-
自分より年下の部下に気を使う
-
上司の無理な指示に逆らえない
-
評価や昇進が“上からの好み”で決まる
このような職場環境では、いくら経験や責任感があっても報われにくく、精神的・身体的な負担が大きくのしかかるのです。
若手や上司からも“挟まれる世代”
世代間ギャップと孤立感
Z世代やミレニアル世代の若手と、昭和的価値観が根強い上司。その間にいる氷河期世代は、どちらとも感覚が合わずに苦しんでいることが多いです。
-
上司からは「もっと積極的に出ろ」と叱責
-
若手からは「空気読めない」と距離を取られる
-
自分だけ指導もされず、評価もされない
こうした現場の“中間管理層未満”のような立ち位置は、孤立と疎外感をもたらし、モチベーション低下の一因にもなっています。
“声を上げない世代”という誤解
氷河期世代は「我慢するのが美徳」とされてきた時代を生きています。そのため、パワハラを受けてもなかなか声を上げられず、結果的に“問題が表に出ない”まま苦しみ続ける傾向があります。
声を上げないことが、“問題がない”と誤解され、支援が後回しになる悪循環も起こっています。
まとめ:構造的に見えない壁を、今こそ意識しよう
氷河期世代は、バブル崩壊後の経済混乱に巻き込まれ、働くチャンスを失っただけでなく、その後の社会構造の中でも長年にわたり見えない圧力やパワハラにさらされ続けてきた世代です。
現在の人手不足社会において、本来であれば最も力を発揮できる世代であるにも関わらず、彼らの声や存在は軽視されがちです。
これから必要なのは、
-
年齢ではなく経験と意欲を重視した採用
-
パワハラのない働きやすい職場の整備
-
世代間の対話と相互理解
-
氷河期世代の“再挑戦”を支える本質的な政策
です。
企業も社会も、一人ひとりがこの世代に対する偏見や誤解を見直すこと。それが、持続可能な労働力の確保につながる大きな第一歩になるはずです。








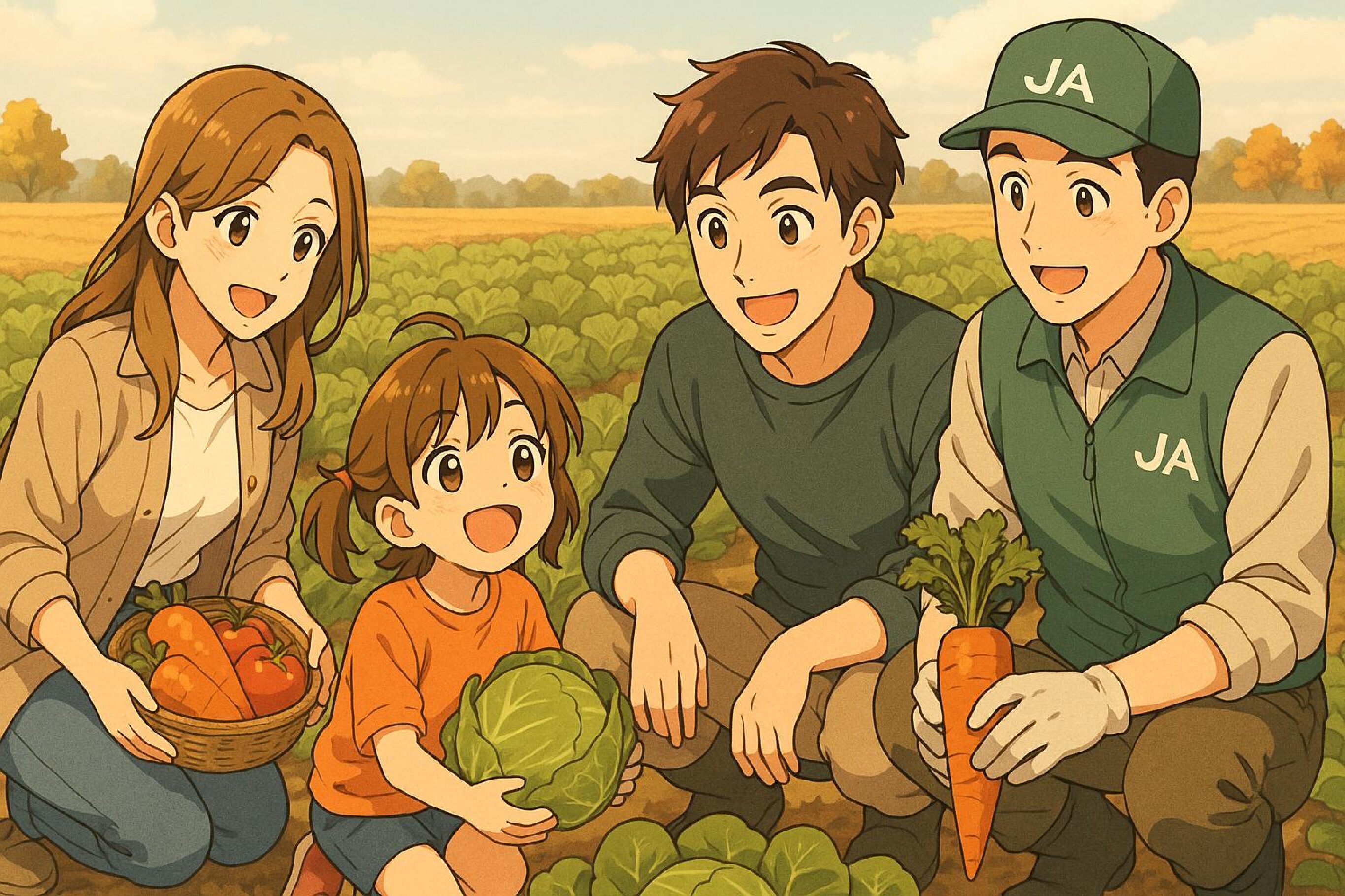







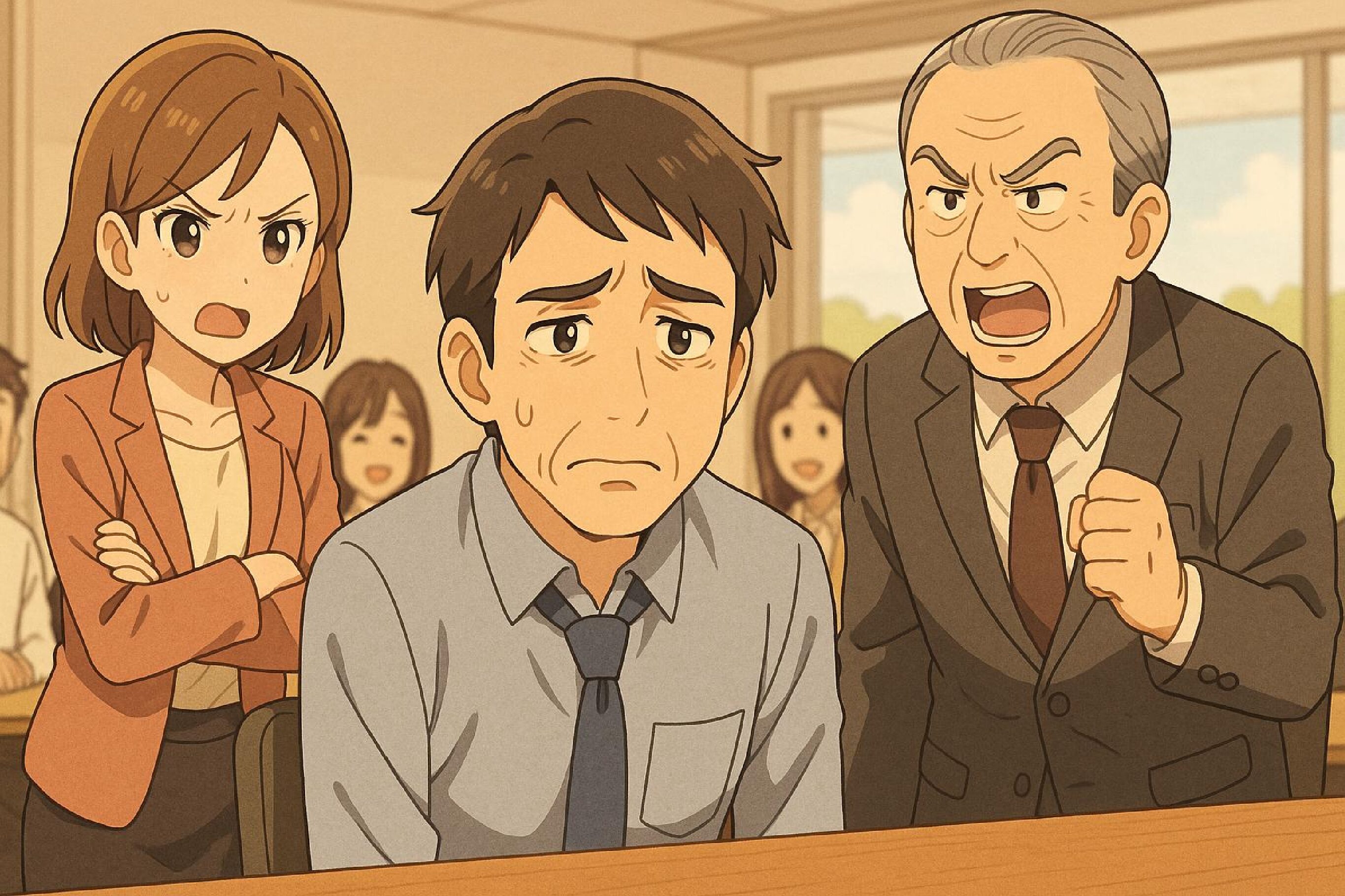

コメント