「うちの子は国語が得意だけど算数が苦手」「音楽は好きなのに、社会になると集中できない」
こうした子どもの学びの姿を前に、親としてどう接すればよいか悩むことは多いものです。
子どもの得意分野を伸ばすべきか、それとも苦手分野を克服させるべきか——この記事では、両方のアプローチにそれぞれどんな意義があり、どのようにバランスを取るべきかを、教育方針に迷う親の視点で考えてみます。
子どもには「得意」と「苦手」があって当然
得意不得意は個性のひとつ
小学生の段階で、得意教科と苦手教科があるのはごく自然なことです。たとえば、
-
文章を読むのが得意=国語や社会が得意
-
数字の処理が速い=算数や理科が得意
-
話すのが上手=道徳や発表が得意
というように、子どもの得意不得意は性格や脳の発達段階とも関係しているため、「苦手がある=劣っている」という見方は正しくありません。
親の思い込みがプレッシャーになることも
「誰でもバランスよくできなければいけない」と思い込んでしまうと、苦手教科への指導が過剰になり、子どもにとっては「叱られることが増える教科」=さらに嫌いになるという悪循環を生むことがあります。
そのため、まずは子どもの得意・苦手を“評価”ではなく“観察”の目で見ることが大切です。
得意を伸ばすメリットと方法
自信を育てる最大の武器になる
得意なことに打ち込むとき、子どもは自然と集中し、成功体験を積み重ねることができます。これは自己肯定感の土台となり、勉強以外の場面でも「自分はできる」という前向きな気持ちを育てます。
たとえば国語が得意な子には、
-
読書量を増やす
-
作文コンクールに挑戦する
-
プレゼンやディスカッションを体験する
といったように、得意を「もっと得意」にする学びの機会を意識的に設けることで、自信が育ちます。
学びの相乗効果が生まれる
意外にも、得意分野を伸ばすことが苦手分野の克服につながるケースもあります。たとえば、
-
国語が得意 → 算数の文章問題の理解力が高まる
-
理科が得意 → 社会の地理や時事に興味が広がる
このように、強みを起点に他教科への興味や理解が深まる“波及効果”が期待できるのです。
苦手を克服するメリットと注意点
将来の“つまずき”を防げる
義務教育ではすべての教科がある程度必要とされます。特に算数や国語などの基礎教科は、進学や社会生活にも直結するため、極端な苦手意識がある場合はある程度の克服が必要です。
-
算数が苦手な場合 → 計算アプリや生活に即した練習で感覚を育てる
-
読解力が弱い場合 → 絵本やマンガなどから語彙を増やす
ポイントは、「できない」ではなく「どうしたら分かるか」を一緒に探す姿勢です。
苦手の克服=努力する力を育てる
苦手なことに少しずつ取り組む体験は、子どもにとって“努力する力”を育てる貴重なチャンスです。すぐに結果が出なくても、「続ける力」「挑戦する姿勢」が身につくことは、人生の大きな財産になります。
ただし注意点として、「苦手を克服しなければならない」という親の強い期待がプレッシャーにならないようにすることが重要です。
親が迷ったときの教育バランスの考え方
「得意=柱」「苦手=足元」と考える
家に例えると、得意分野はその子の“柱”であり、苦手分野は“足元”です。柱をしっかり太くしてあげることで、足元のぐらつきも自然と安定していくのです。
-
柱(得意)をどんどん伸ばして自信を育てる
-
足元(苦手)はぐらつかない程度に補強する
このように、両方のバランスを取りながら育てるイメージが、子どもの学びの成長には効果的です。
週単位・月単位で「注力ポイント」を分けてみる
「得意だけだと不安」「苦手ばかりでは嫌になりそう」——そんなときは、週ごと・月ごとにテーマを変えるのも一つの方法です。
-
今週は算数の文章問題を集中的に
-
今月は読書感想文に挑戦してみる
-
来週は理科実験イベントに参加する
このように、学びの対象を区切ることで親も子も気持ちが楽になり、メリハリのある学習ができます。
子どもの個性を尊重する親のかかわり方とは?
「得意を認める」「苦手を否定しない」が基本
子どもの能力や性格に合った接し方を意識するには、
-
得意なことは積極的に褒める
-
苦手なことには焦らず寄り添う
-
「できたね」よりも「よく考えたね」とプロセスを評価する
といった声かけや態度が大切です。得意・不得意を含めた個性をまるごと受け入れる姿勢が、子どもの学びに向かう力を引き出します。
教育のゴールは「学力」より「自己肯定感」
子育てで最も大切なのは、「この子が自分らしく学び続けていける力を育てること」です。学力や成績はその一部であり、目的ではありません。
-
得意を伸ばして自信をつける
-
苦手と向き合って努力する力を育てる
-
親が寄り添うことで安心感を与える
こうした小さな積み重ねが、将来の学びの土台や生きる力をつくっていきます。
まとめ:得意も苦手も、その子の“今”を認めることが第一歩
得意をもっと得意にするのか、苦手を少しでも克服するのか。その選択に正解はありません。子どもの個性やタイミングに応じて、柔軟に方針を変えていくことも大切です。
-
得意=自信の源、伸ばして正解
-
苦手=支え方次第で学ぶ力に
-
親の役目は「導く」より「支える」こと
迷ったときには、「この子にとって一番楽しく学べる方法はどれか?」という問いに立ち返ってみましょう。それが、親子にとっての一番の学びのヒントになるはずです。








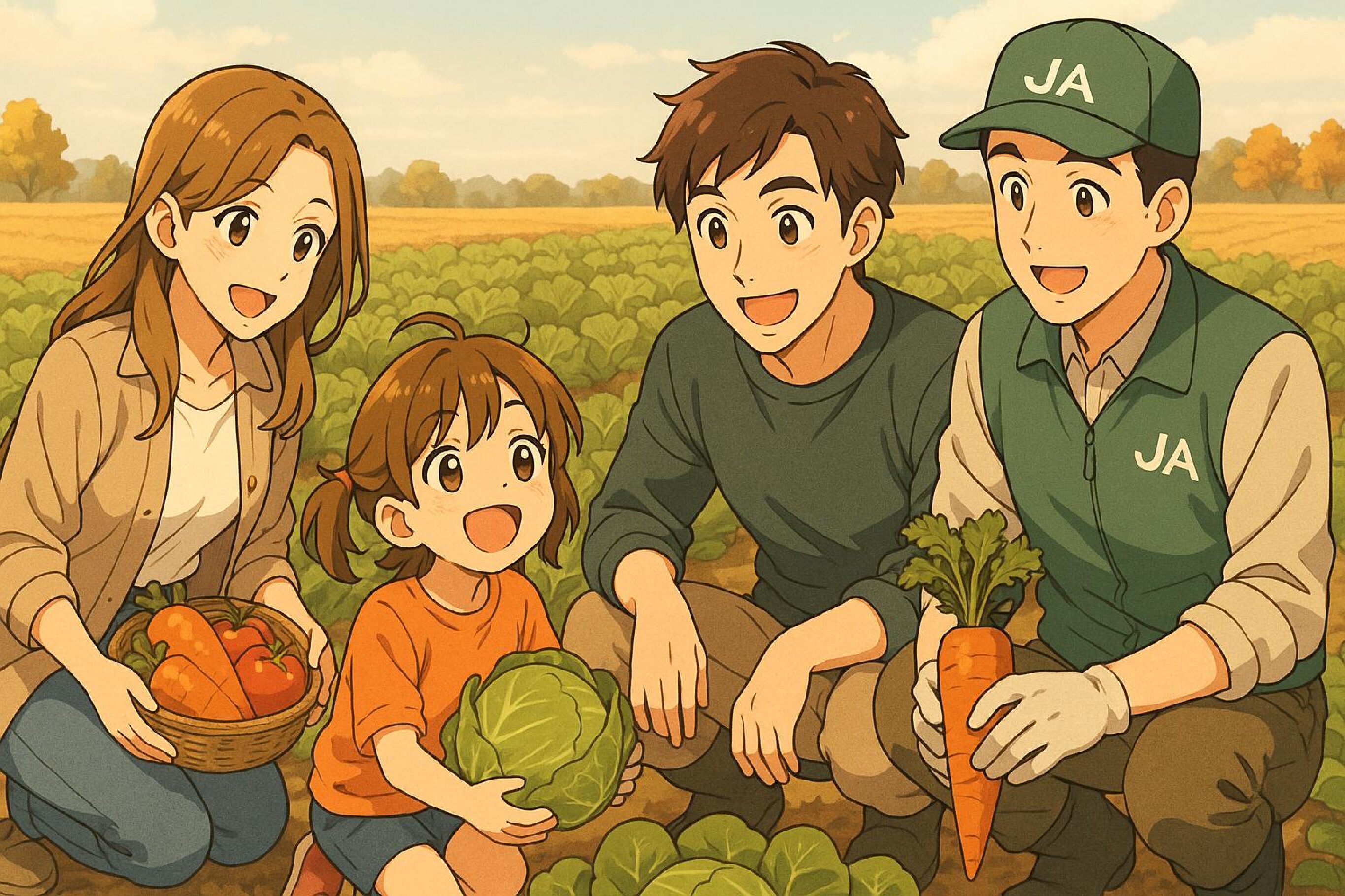








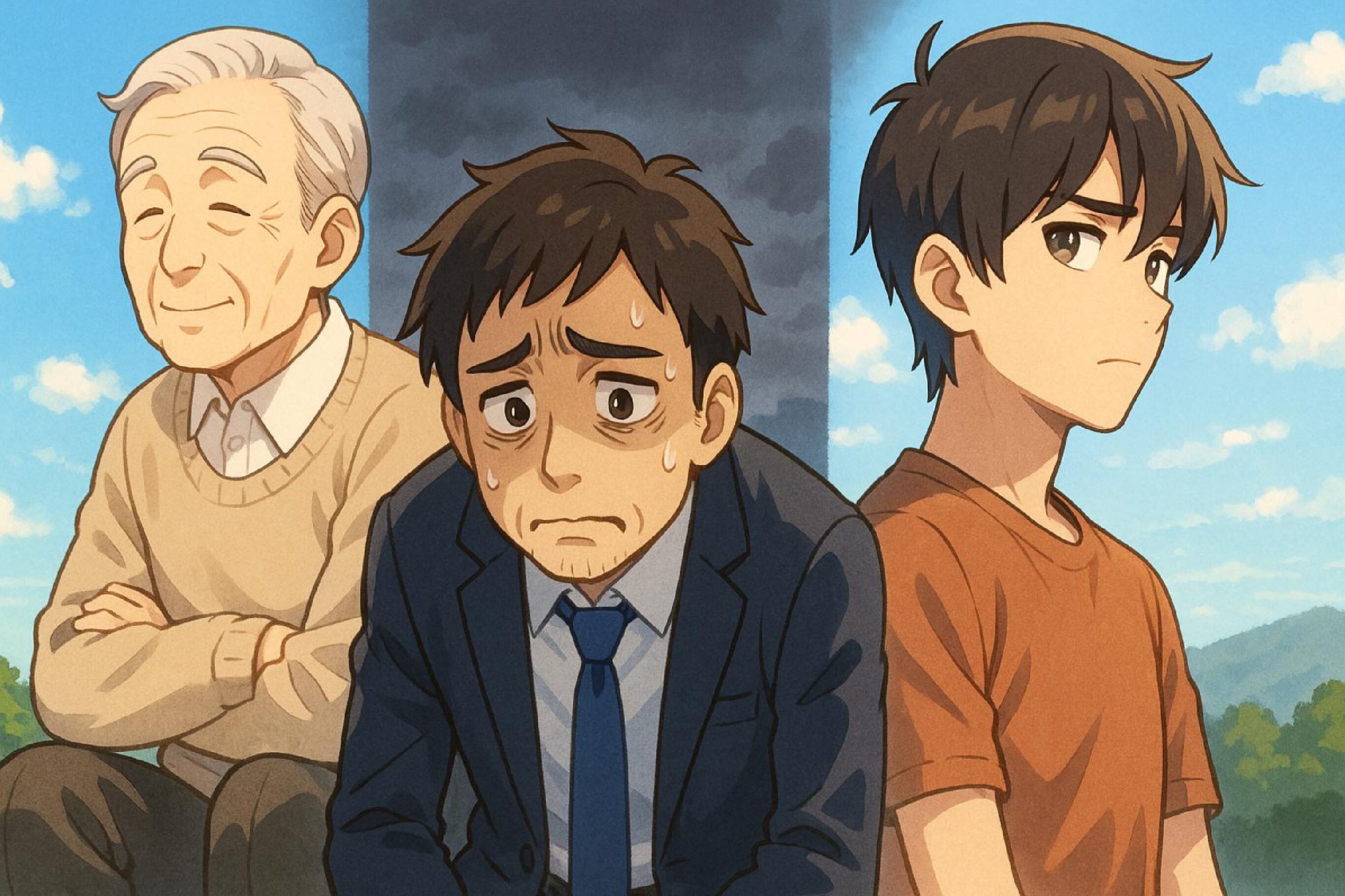
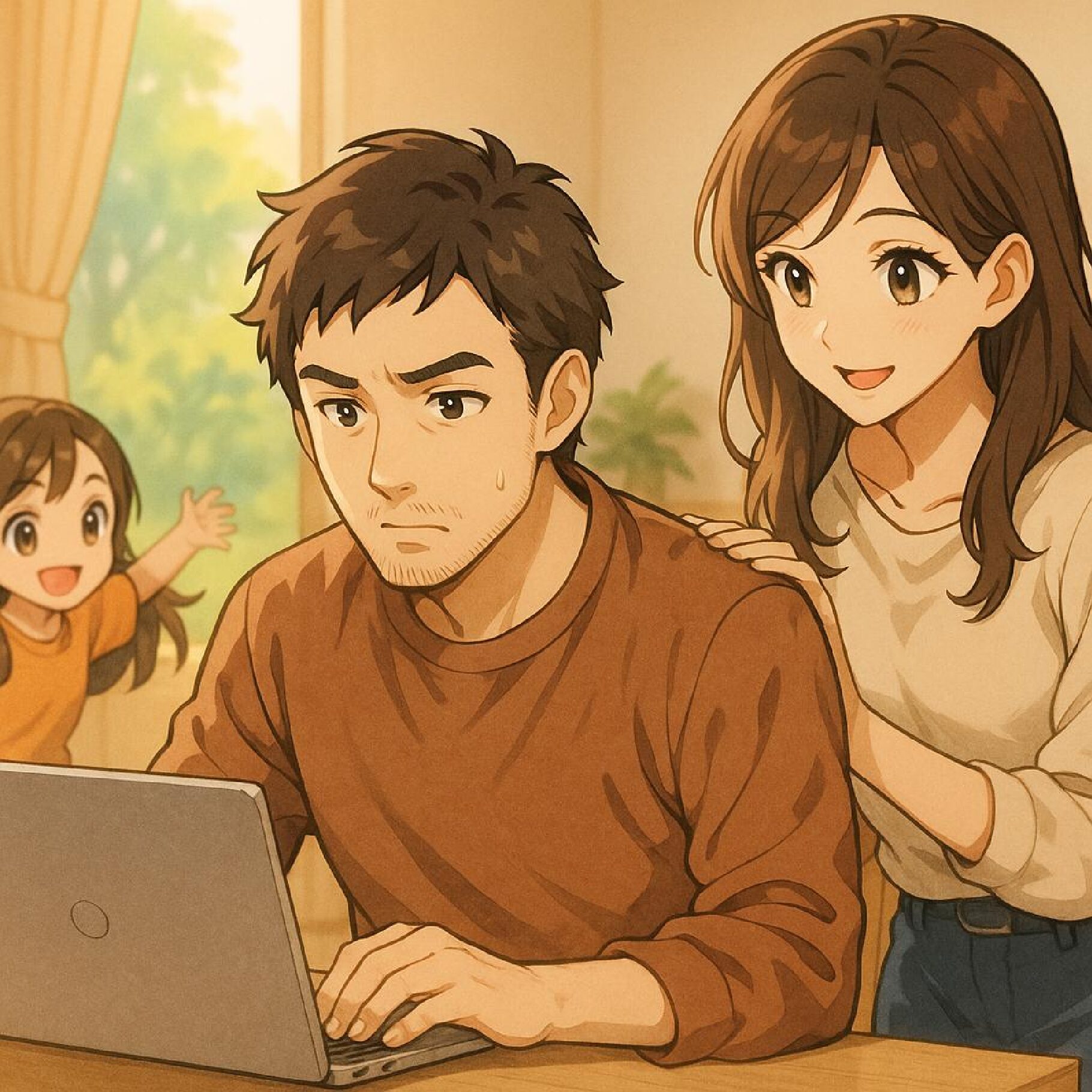
コメント