「ステマ」という言葉を聞いたことはあるけれど、正確な意味や事例、そして規制の内容についてよく知らないという人も多いのではないでしょうか。
近年、SNSや口コミサイトを中心に問題視され、法律による規制も強化されています。
この記事では、ステマ(ステルスマーケティング)の意味や特徴、実際の事例、そして規制のポイントをわかりやすく解説します。
ステマとは何か?
ステルスマーケティングの意味
ステマとは「ステルスマーケティング」の略で、消費者に広告であることを隠して宣伝を行う手法です。
通常の広告は「PR」や「広告」といった表記がありますが、ステマはあたかも“自然な口コミ”や“個人の感想”のように見せかけて、商品やサービスを宣伝する点が特徴です。
ステマが問題視される理由
-
消費者をだます行為につながる
-
誇大表現や虚偽の情報が含まれる場合がある
-
企業やインフルエンサーの信頼を大きく損なう
消費者保護の観点からも、ステマは大きな社会問題として取り上げられています。
ステマの代表的な事例
芸能人やインフルエンサーによるSNS投稿
芸能人やインフルエンサーが、実際には企業から報酬を受けているのに「私のお気に入りです!」と自然な宣伝のように発信するケースがあります。
口コミサイトでのやらせ投稿
レストランや美容商品の口コミを、企業が自ら高評価で投稿したり、外注ライターに依頼して書かせるケースも典型的なステマです。
動画配信での隠れ広告
YouTubeなどの動画配信で、案件であることを隠して商品紹介を行う場合もステマに該当します。
日本でのステマ規制のポイント
消費者庁による広告表示のルール
2023年10月から、ステマが景品表示法違反の「不当表示」として規制対象になりました。これにより、企業がインフルエンサーに依頼して広告を出す際は、「PR」「広告」など明示することが義務化されました。
違反した場合のリスク
-
企業名の公表
-
行政処分
-
社会的信用の失墜
規制が強化されたことで、企業・インフルエンサー双方に大きな責任が生じています。
ステマと合法的な広告の違い
表記があるかどうか
-
合法的な広告:必ず「PR」「広告」「提供」などの表記あり
-
ステマ:広告であることを隠して宣伝する
消費者が見抜けるか
広告であると明示されていれば、消費者は「宣伝」と認識して判断できます。
一方でステマは消費者の判断をゆがめるため、違法性が高いとされています。
ステマが消費者に与える影響
誤った購買判断につながる
本当に良い商品だと思い込んで購入してしまう可能性があります。
ブランドへの不信感を生む
後から「実はステマだった」とわかると、そのブランドやインフルエンサーへの信頼を一気に失います。
社会的炎上リスク
SNSで拡散されることで、企業全体のイメージダウンに直結します。
企業・インフルエンサーが気をつけるべきこと
明確な広告表記を行う
「#PR」「広告」「提供」などのハッシュタグや表記を必ず付けましょう。
透明性のある発信を意識する
消費者が誤解しないよう、宣伝であることを前提に正しい情報を発信する姿勢が大切です。
信頼を守る行動を取る
一時的な売上よりも、長期的なブランド価値を優先することが結果的にメリットになります。
ステマを見抜く消費者の視点
不自然なほどの絶賛レビュー
口コミやSNSで「すごい!最高!絶対おすすめ!」と過剰な褒め言葉が続く場合、ステマの可能性があります。
同じ表現が多く使われている
複数のレビューで同じ言葉や文章が繰り返されている場合も不自然です。
広告表記がないインフルエンサー投稿
フォロワーの多い人が特定の商品を頻繁に紹介しているのに「PR」表記がない場合は注意が必要です。
まとめ|ステマを正しく理解しよう
-
ステマとは広告であることを隠して宣伝する行為
-
SNSや口コミサイトで多く見られ、消費者をだますリスクがある
-
日本では2023年から規制が強化され、違反すると企業名公表や処分の対象になる
-
インフルエンサーや企業は「広告表記」を徹底することが必須
-
消費者も「不自然なレビューや投稿」を疑う視点を持つことが大切
ステマを正しく理解することで、私たちは賢い購買行動を選択できます。企業やインフルエンサーも透明性を重視し、信頼される情報発信を心がけることが求められています。

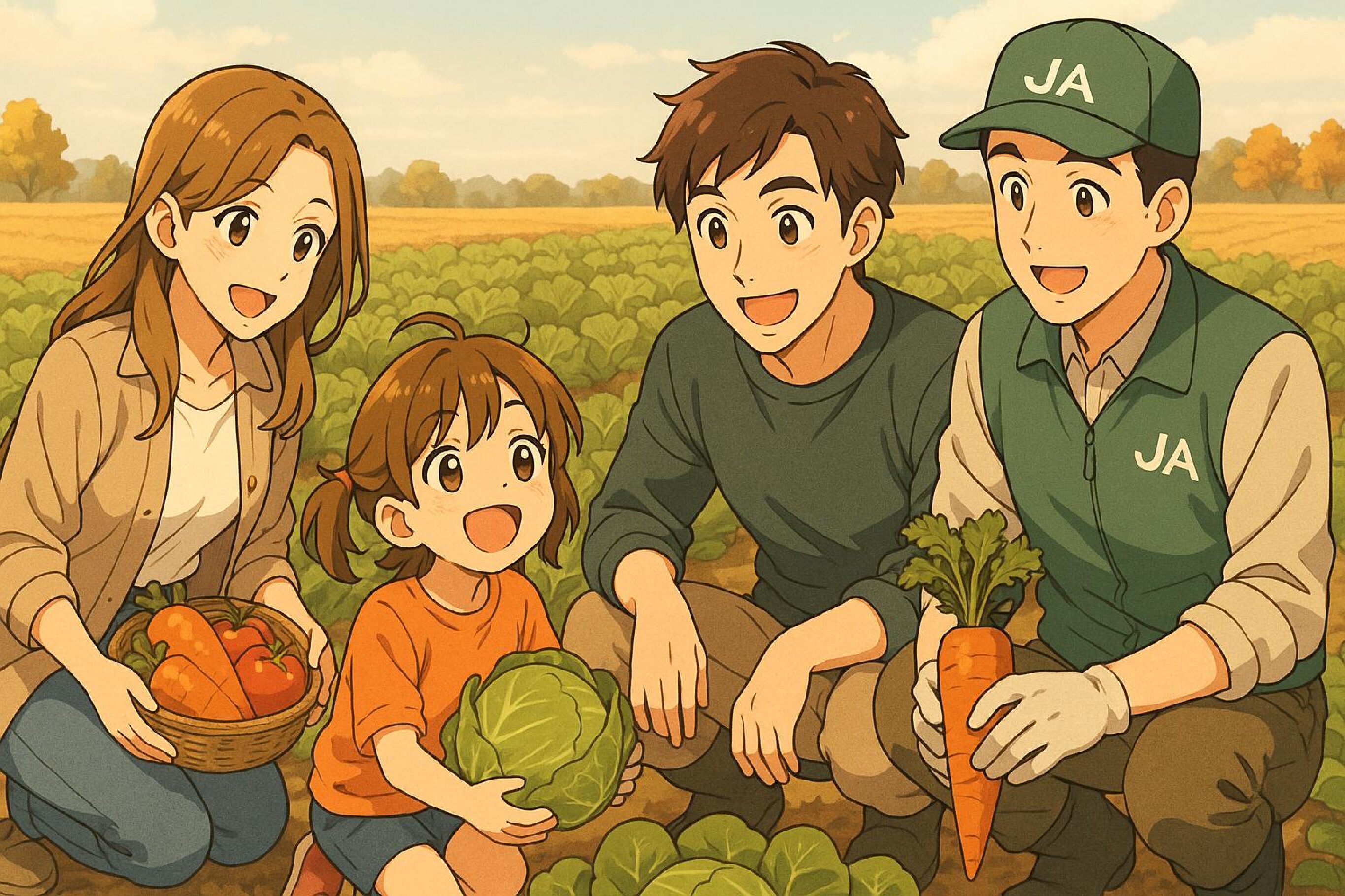

















コメント